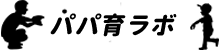はじめに

2025年4月、育児介護休業法が大きく変わります。「子育てしながら働きたいけど、制度が複雑でよくわからない」「パートナーと育児を分担したいけど、会社の制度はどうなってるの?」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回の改正は、男女ともに仕事と育児を両立しやすくするための大きな一歩です。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、2025年4月施行の育児介護休業法改正のポイントを分かりやすく解説します。
2025年4月改正の3つの柱

今回の改正は、大きく分けて3つの柱で構成されています。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現
- 育児休業取得状況の公表義務拡大
- 介護離職防止のための支援強化
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 子育て世代の柔軟な働き方が実現

小学3年生まで使える「柔軟な働き方」制度
これまで3歳未満の子どもを持つ親にしか認められていなかった支援が、大幅に拡充されます。
3歳から小学校就学前の子を育てる労働者は、会社が用意する以下5つの制度のうち2つ以上から選んで利用できるようになります。
- 始業時刻の変更(フレックスタイム制、時差出勤など)
- テレワーク(月10日以上)
- 保育施設の設置運営
- 養育両立支援休暇(年10日以上)
- 短時間勤務制度
この制度は2025年10月から施行されます。
子の看護休暇が「子の看護等休暇」に進化
対象年齢が小学3年生修了まで延長され、取得理由も拡大します。
改正前
- 対象:小学校就学前まで
- 理由:病気・けが、予防接種・健康診断
改正後
- 対象:小学3年生修了まで
- 理由:上記に加えて
- 感染症に伴う学級閉鎖等
- 入園式・入学式・卒園式
年間5日(子が2人以上の場合は10日)取得できる日数は変わりません。
残業免除の対象が拡大
所定外労働の制限(残業免除)の対象が、3歳未満から小学校就学前まで拡大されます。
保育園のお迎えなど、定時で帰らなければならない状況に対応しやすくなります。
短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加
3歳未満の子を育てる労働者向けの短時間勤務制度について、業務の都合で短時間勤務が難しい場合の代替措置にテレワークが追加されました。
働き方の選択肢が広がることで、より多くの人が仕事と育児を両立しやすくなります。
2. 個別の意向聴取と配慮が義務化

妊娠・出産時と子が3歳になる前の面談
会社は、以下のタイミングで労働者の意向を個別に聴取し、配慮することが義務付けられます。
意向聴取のタイミング
- 本人または配偶者の妊娠・出産等の申出時
- 子が3歳になるまでの適切な時期
聴取する内容
- 勤務時間帯(始業・終業時刻)
- 勤務地
- 両立支援制度の利用期間
- 業務量や労働条件の見直し
この制度により、一人ひとりの状況に合わせた働き方が実現しやすくなります。
定期的な面談も推奨
育児休業後の復職時や、短時間勤務制度利用中など、定期的に面談を行うことが望ましいとされています。
家庭や仕事の状況は変化するため、継続的なコミュニケーションが重要です。
3. 育児休業取得状況の公表義務が拡大

従業員数300人超の企業(改正前は1,000人超)に、男性の育児休業取得率の公表が義務付けられます。
年1回、インターネット等で一般に公開する必要があります。
これにより、企業の取り組み状況が可視化され、育児休業を取りやすい職場環境づくりが促進されることが期待されます。
4. 介護離職を防ぐための支援も強化
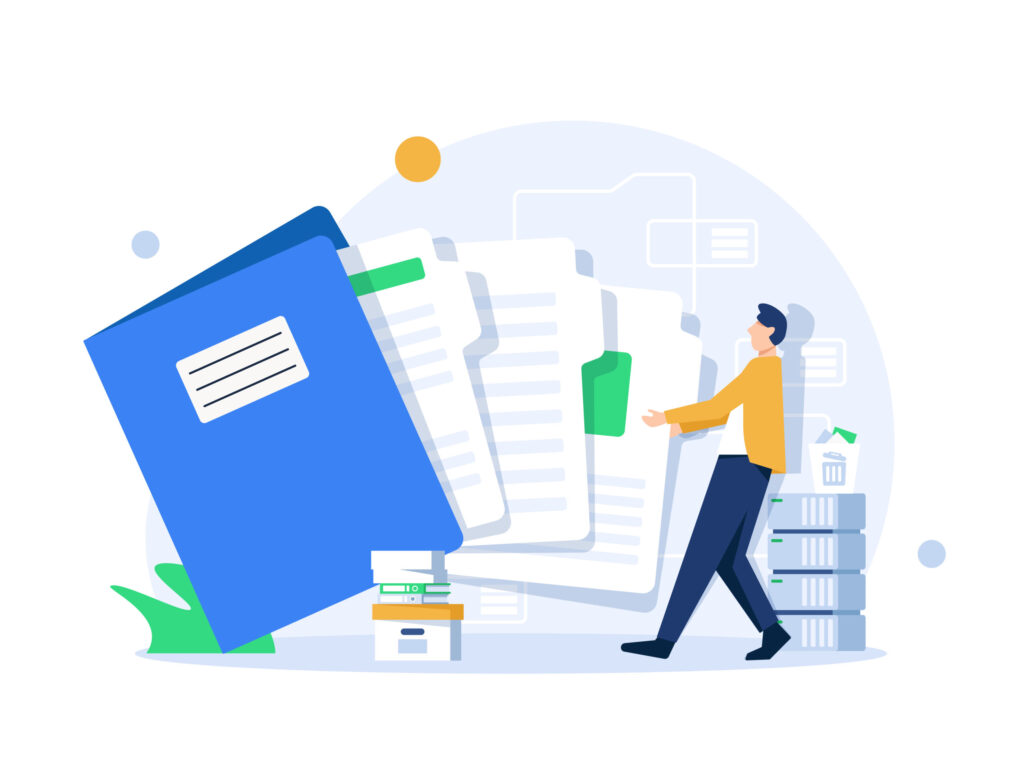
育児だけでなく、介護との両立支援も強化されます。
介護に直面したときの個別周知・意向確認
労働者が家族の介護に直面した旨を申し出たときに、会社は以下を行う義務があります。
- 介護休業や両立支援制度の個別周知
- 制度利用の意向確認
40歳時点での情報提供
介護に直面する前の早い段階(40歳など)で、介護休業制度等について情報提供することが義務付けられます。
雇用環境の整備
以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
- 介護休業・両立支援制度等に関する研修の実施
- 相談窓口の設置
- 制度利用事例の収集・提供
- 利用促進に関する方針の周知
介護休暇の要件緩和
勤続6か月未満の労働者を労使協定で除外できる仕組みが廃止されます。
改正法を活用するための5つのポイント

1. 会社の制度を確認する
2025年4月以降、会社がどのような制度を用意しているか、就業規則や人事部に確認しましょう。
特に「柔軟な働き方を実現するための措置」では、会社が選択した2つ以上の制度から自分で選べます。
2. 早めに意向を伝える
妊娠・出産の申出や、子が3歳になる前の面談の機会を活用して、自分の希望する働き方を会社に伝えましょう。
具体的に「こういう働き方がしたい」と伝えることで、会社も配慮しやすくなります。
3. パートナーと育児計画を話し合う
夫婦で育児をどう分担するか、それぞれどんな制度を利用するか、事前に話し合っておくことが大切です。
特に男性の育児休業取得は、今後ますます重要になります。
4. 制度の目的を理解する
育児休業は「育児の体制を構築するため」、短時間勤務は「育児との両立のため」など、各制度には目的があります。
目的を理解した上で、自分に合った制度を選びましょう。
5. 定期的に見直す
子どもの成長や家庭の状況に応じて、利用する制度を見直すことも大切です。
会社との定期的な面談を活用しましょう。
よくある質問

Q1. パートやアルバイトでも制度は使えますか?
はい、基本的には雇用形態に関わらず利用できます。ただし、週の所定労働日数が2日以下の場合は、一部の制度で除外される可能性があります。
Q2. 制度を利用すると評価や昇進に影響しますか?
法律上、育児休業等の取得を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。もし不当な扱いを受けた場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
Q3. 男性も育児休業を取れますか?
もちろんです。出生時育児休業(産後パパ育休)など、男性向けの制度も充実しています。今回の改正でも、男性の育児参画を促進する内容が盛り込まれています。
Q4. テレワークを選択した場合、毎日在宅勤務できますか?
「柔軟な働き方を実現するための措置」でのテレワークは、月10日以上利用できることが条件です。毎日在宅勤務になるかは会社の制度次第です。
Q5. 今働いている会社が制度を用意していない場合は?
2025年4月以降は、法律で義務付けられているため、会社は制度を整備する必要があります。もし整備されていない場合は、人事部や労働局に相談しましょう。
まとめ

2025年4月の育児介護休業法改正は、働きながら子育てや介護をする人にとって大きな追い風となります。
改正のポイント
- 小学3年生まで柔軟な働き方が選べる
- 子の看護等休暇が使いやすくなる
- 個別の意向聴取と配慮が義務化
- 男性の育児休業取得率の公表義務拡大
- 介護離職防止の支援強化
制度を最大限活用するためには、早めの情報収集と会社とのコミュニケーションが大切です。
この記事が、仕事と家庭の両立を目指すあなたの一助となれば幸いです。
お問い合わせ先 育児・介護休業法に関する相談は、お住まいの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ 受付時間:8時30分〜17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」