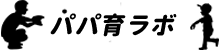はじめに

「また走り回って。もう何度言ったらわかるの!」
「どうして言うことを聞かないの?」
「片付けができない子になっちゃうよ…」
子育て中のパパなら、このような言葉を口にしたことがあるのではないでしょうか。子どもの「困った行動」に頭を抱え、つい感情的な声かけをしてしまう—そんな経験は誰にでもあります。
しかし、子どもの「困った行動」は、実は隠れた才能や資質の表れかもしれません。同じ行動でも、視点を変えれば「才能の芽」として捉えることができるのです。そして、その芽を育てるのに最も効果的なのが、パパの声かけなのです。
本記事では、子どもの「困った行動」の裏にある才能を見抜き、それを伸ばす声かけテクニックを、パパの視点からご紹介します。このテクニックを習得すれば、日々の子育てがより前向きで楽しいものになるでしょう。
なぜパパの声かけが重要なのか?その科学的根拠

「なんでパパが特別なの?ママでも同じじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。もちろん、母親の子育ても極めて重要です。しかし、父親と母親では脳の構造や反応パターンに違いがあり、子どもへの影響も異なります。
東京大学の発達心理学研究によると、父親の関わり方は「挑戦を促す」「リスクテイクを教える」「外の世界とつなげる」という特徴があります。これらは子どもの社会性や自立心の発達に不可欠な要素です。
特に注目すべきは、父親からの肯定的なフィードバックが子どものレジリエンス(困難に立ち向かう力)を高めるという研究結果です。アメリカの小児科学会も「父親の積極的な育児参加が子どもの認知能力や感情制御能力の発達に重要な役割を果たす」と指摘しています。
つまり、パパの声かけには子どもの才能を開花させる特別な力があるのです。では、その力を最大限に活かすにはどうすればよいのでしょうか。
才能に変換できる「困った行動」5つのタイプ

子どもの困った行動には、実はいくつかのパターンがあります。それぞれの行動の裏にある才能を理解し、適切な声かけができるようになりましょう。
【タイプ1】落ち着きがない・じっとしていられない
レストランで座っていられない、電車で立ち歩く、授業中に席を離れるなど、「落ち着きのなさ」に悩むパパは多いでしょう。
隠れた才能: 好奇心旺盛・探求心・身体的エネルギー
このタイプの子どもは、世界への強い好奇心と探求心を持っています。また、身体を動かすことで学習する「身体感覚学習型」の可能性があります。将来、スポーツ選手や冒険家、フィールドワーク系の職業に向く資質かもしれません。
NG例: 「もう、じっとしていられないの?」「落ち着きがなくて困るね」
OK例: 「いろんなことが気になるんだね。その好奇心、すごいよ!」「体を動かすの好きだね。この後公園で思いっきり走ろうか」
【タイプ2】言うことを聞かない・反抗的
「ダメ」と言われても繰り返す、「なんで?」と質問を繰り返す、ルールに従わないなど、言うことを聞かない行動は親を試す場合が多いです。
隠れた才能: 独立心・リーダーシップ・自己主張力
このタイプの子どもは、自分の意見を持ち、それを表現しようとする強い独立心を持っています。将来のリーダーや起業家、革新者になる可能性を秘めています。
NG例: 「どうして言うことを聞けないの?」「反抗ばかりして」
OK例: 「自分の考えをしっかり持っているね。それは大事なことだよ」「なぜそう思うのか、パパに教えてくれる?」
【タイプ3】感情の起伏が激しい・かんしゃく
ささいなことで大泣きする、怒りを爆発させる、感情のコントロールができないように見える行動です。
隠れた才能: 感受性・情熱・共感力
このタイプの子どもは、感情が豊かで、物事を深く感じ取る能力を持っています。芸術家や作家、カウンセラーなど、感情を活かす職業に向いているかもしれません。
NG例: 「そんなことで泣くの?」「いちいち大げさだね」
OK例: 「そんなに悲しかったんだね。気持ちをわかってほしいんだよね」「感情表現が豊かなことは、素晴らしい才能だよ」
【タイプ4】こだわりが強い・融通が利かない
いつも同じ服を着たがる、食べ物の配置にこだわる、ルーティンを変えたがらないなど、柔軟性のなさが気になる行動です。
隠れた才能: 集中力・専門性・完璧主義
このタイプの子どもは、細部に注意を払い、物事を深く追求する能力を持っています。科学者、エンジニア、専門家など、特定分野での深い知識や技術を必要とする職業に向いているでしょう。
NG例: 「もっと柔軟になりなさい」「いつもワガママばかり」
OK例: 「細かいところまでよく見ているね!」「自分のやり方を大切にしているんだね。それは素敵なこと」
【タイプ5】夢見がち・空想好き
現実と空想の区別がつかない、空想の友達と話す、授業中にボーっとしているなど、集中力がないように見える行動です。
隠れた才能: 創造性・想像力・芸術的センス
このタイプの子どもは、豊かな想像力と創造性を持っています。アーティスト、クリエイター、発明家など、独創的なアイデアを生み出す職業に向いているかもしれません。
NG例: 「現実を見なさい」「いつもボーっとして」
OK例: 「どんなことを想像していたの?聞かせてくれる?」「そんな素敵なアイデアを思いつくなんて、すごい想像力だね!」
声かけの基本:PAC法の紹介

子どもの困った行動に対して効果的に声かけをするための基本的な方法として、「PAC法」をご紹介します。これは特にパパの声かけに適した方法です。
P = Pause(一旦立ち止まる)
子どもの行動に反射的に反応する前に、一呼吸置きましょう。感情的になると、ついネガティブな言葉が出やすくなります。
実践方法:
- 大きく深呼吸をする
- 心の中で10秒カウントする
- 「これは緊急事態か?」と自問する
研究によれば、わずか3秒の間を置くだけでも、より冷静で建設的な対応ができるようになります。
A = Appreciate(認める)
子どもの行動の背景にある感情や意図を認めましょう。すべての行動には何らかの理由があります。
実践方法:
- 「なぜこの行動をしているのだろう?」と考える
- 子どもの視点から状況を見る
- 行動の裏にある前向きな意図や才能を探す
例えば、食事中に立ち歩く行動の裏には、「エネルギーが有り余っている」「新しいことを発見したい」という前向きな衝動があるかもしれません。
C = Connect(つながる)
共感と理解を示しながら声かけをします。子どもは自分が理解されていると感じると、より前向きに変化します。
実践方法:
- 子どもと同じ目線に立つ(物理的に目の高さを合わせる)
- 「〜だね」「〜なんだね」と共感の言葉を使う
- 指示や命令ではなく、選択肢を提示する
例:「走りたい気持ちはわかるよ。今は室内だから、この後公園で思いっきり走ろうか?それとも、家の中ではこのゲームで体を動かしてみる?」
PAC法の実践において、パパ特有の注意点として、声のトーンと身体的距離があります。パパの声は一般的に低く響きが強いため、意図せず子どもを威圧する可能性があります。意識的に穏やかなトーンを心がけましょう。また、身体的な距離も子どもが安心できる範囲を保つことが大切です。
年齢別・効果的な声かけフレーズ集

子どもの年齢によって、効果的な声かけは異なります。年齢ごとの発達段階を考慮したフレーズをご紹介します。
2〜3歳向け:シンプルで具体的なフレーズ
この年齢の子どもは、短く具体的な言葉をよく理解します。抽象的な説明は避け、ポジティブな表現を心がけましょう。
- 「その力の使い方、すごいね!」(暴れている時)
- 「手を強く押すんじゃなくて、優しくタッチしてみよう」(叩く代わりに)
- 「そんなに走れるなんて、足が強いね!」(走り回る時)
- 「その声、遠くまで届くね!」(大声を出す時)
- 「そのブロック、面白い形にできたね!」(物を投げる代わりに)
- 「待てるかな?パパと一緒に数を数えよう」(待てない時)
- 「自分でやりたいんだね、すごい!」(反抗的な時)
- 「その気持ち、言葉で教えて」(泣き叫ぶ時)
- 「今は◯◯の時間だよ」(ルーティンを教える時)
- 「パパと一緒にやってみようか?」(挑戦を促す時)
4〜5歳向け:理由を添えた説明フレーズ
この年齢になると「なぜ?」という質問が増え、理由を理解する力が発達します。簡単な説明と共に、ポジティブな側面を伝えましょう。
- 「その好奇心、素晴らしいね。でも室内では別の方法で試してみよう」
- 「自分の考えをはっきり言えるのはすごいこと。でも相手の気持ちも大切だよ」
- 「そんなに感情を表現できるなんて素敵。でも落ち着く方法も知っておこうね」
- 「細かいところまで気にできるのは特別な力だよ。いろんなやり方も試してみようか」
- 「そんな素敵な想像ができるなんて!その話、もっと聞かせて」
- 「失敗しても大丈夫。チャレンジする勇気がすごいね」
- 「自分でできることが増えてきたね。パパも手伝うよ」
- 「そのアイデア面白いね。もっと安全にできる方法を一緒に考えようか」
- 「怒りたい気持ちわかるよ。でも言葉で伝える練習をしよう」
- 「そんなに集中できるなんてすごい!時間を決めて楽しもうね」
小学生低学年向け:対話型フレーズ
この年齢では、自分の考えや感情を言葉で表現する力が育ちます。子ども自身に考えさせる対話型の声かけが効果的です。
- 「どうしてそう思ったの?もっと教えてくれる?」
- 「その方法は面白いね。他にどんな方法があると思う?」
- 「どうすれば次はうまくいくと思う?パパも一緒に考えるよ」
- 「その気持ち、どんな言葉で表現できる?」
- 「自分ならどうしてほしい?相手の気持ちを想像してみよう」
- 「その問題、どうやって解決したらいいと思う?」
- 「何がそんなに面白いと感じるの?もっと詳しく聞かせて」
- 「その得意なことを活かして、こんなことができるかもね」
- 「失敗から何を学んだ?次はどうしたい?」
- 「その行動にはどんな結果が起きると思う?」
小学生高学年向け:自己認識を促すフレーズ
この年齢では、自己認識や自己調整の能力が発達します。子ども自身の強みを認識させ、それを活かす方向に導く声かけが効果的です。
- 「君のそういう特徴は、実は大きな強みになるんだよ」
- 「その情熱をどんなことに活かせると思う?」
- 「自分の感情をよく理解できているね。それは大人でも難しいことだよ」
- 「その考え方は独創的だね。そういう視点が社会を変えるんだよ」
- 「細部まで気にできる力は、将来どんな場面で役立つと思う?」
- 「自分の長所と短所、どんなところだと思う?」
- 「自分らしさを大切にしながら、どうやって周りと協力できると思う?」
- 「今の状況を変えるために、自分にできることは何だろう?」
- 「その経験から学んだことを、次にどう活かせそう?」
- 「自分の行動が他の人にどんな影響を与えると思う?」
各年齢層での声かけにおいて、パパならではのポイントは「挑戦を促す」「失敗を恐れない姿勢を教える」「論理的思考を育む」という点です。特に男性は女性に比べて、子どもに適度なリスクテイクを促す傾向があり、これが子どもの自信や問題解決能力の発達に良い影響を与えるといわれています。
【実践編】シーン別対応テクニック

日常生活の中で特に「困った」と感じやすいシーンごとに、具体的な対応方法をご紹介します。
公共の場での困った行動
レストランや電車、スーパーなど、公共の場での子どもの行動に困ることは多いものです。
即効性のある声かけ法:
- 事前の期待値設定:「これからお店に行くよ。お店ではこんなふうに過ごそうね」
- 選択肢の提示:「走りたい気持ちはわかるけど、ここは走る場所じゃないね。代わりに〇〇をしようか?」
- 「ミッション」の設定:「今日はお買い物探検隊だよ。このリストのものを見つける手伝いをしてくれる?」
筆者体験談: 3歳の息子は、スーパーでカートに乗りたがり、断ると大泣きする困った行動がありました。「カートに乗るのではなく、カートを押す立派なお手伝いをしてもらえるかな?」と提案すると、突然誇らしげな表情に変わり、とても協力的に。子どもは「役割」と「信頼」を求めているんだと実感しました。
兄弟姉妹間のトラブル
兄弟姉妹間のけんかやトラブルは、多くの家庭の悩みの種です。
公平さを保ちながらの介入法:
- 双方の話を聞く:「二人の話をそれぞれ聞かせて」
- 解決法を考えさせる:「二人はどうしたら仲良く遊べると思う?」
- 協力の機会を作る:「二人で力を合わせないとできないゲームがあるよ」
筆者体験談: 兄と弟のおもちゃの取り合いが毎日のように発生していました。「このおもちゃはとても人気者だね。みんなに遊んでもらいたいんだね」と、おもちゃの視点を取り入れた声かけをすると、子どもたちは笑い出し、「じゃあ交代で遊ぼう」と自分たちで解決策を見つけるようになりました。
宿題・勉強のさぼり
学校の宿題や勉強を避けたがる子どもへの対応は、多くのパパの悩みです。
やる気を引き出す声かけ:
- 好奇心につなげる:「この問題、パパも解けるか挑戦してみようか?」
- 選択権を与える:「最初に国語からする?それとも算数?」
- 時間を区切る:「15分だけ集中してやってみよう。タイマーをセットするね」
筆者体験談: 6歳の息子が幼稚園の絵日記を週末に書くのを嫌がるのに悩んでいました。「パパとどっちが絵が上手に書けるかな?」と提案し、絵を上手さを競うゲームに変えたところ、週末の絵日記が嫌がらなくなりました。「競争」と「遊び」の要素を入れることで、学習への抵抗感が減りました。
スクリーンタイムをめぐる戦い
テレビやゲーム、スマホなどのスクリーンタイムをめぐるバトルは現代の親子間で最も一般的な問題の一つです。
ポジティブな切り替え方:
- 明確なルール設定:「スクリーンタイムは1日30分までね。タイマーをセットしよう」
- 代替活動の提案:「ゲームの後は、一緒に新しい実験をしてみない?」
- 興味の橋渡し:「そのゲームのキャラクターみたいな絵を描いてみようか?」
筆者体験談: 6歳の息子がゲームをやめられず、毎回親子バトルになっていました。「あと5分でゲームはおしまいだよ」と前もって伝え、さらに「その後は一緒にLEGOでそのゲームに出てくる乗り物を作ろう!」と提案したところ、スムーズな切り替えができるようになりました。デジタルからアナログへの自然な橋渡しが効果的でした。
就寝時の抵抗
「もう少し起きていたい」「まだ遊びたい」と、就寝を嫌がる子どもへの対応に悩むパパは多いでしょう。
スムーズな就寝ルーティンへ導く声かけ:
- 予告する:「あと10分したら寝る準備を始めようね」
- ルーティン化する:「パジャマに着替えて、歯を磨いて、絵本を読んで、おやすみなさい」
- 選択権を与える:「今日はどの絵本を読む?」「ライトの色は青にする?それとも緑?」
筆者体験談: 6歳の息子が毎晩寝るのを嫌がってぐずっていました。「眠る時間は終わりじゃなくて、夢の冒険の始まりだよ」と伝え、「今夜はどんな夢を見たい?」と想像を膨らませる会話を寝る前に取り入れたところ、寝ることへの抵抗が減りました。就寝を「失うもの」ではなく「得るもの」として捉え直す声かけが効果的でした。
パパの声かけが子どもの脳に与える長期的な効果

適切な声かけは、単に目の前の「困った行動」を減らすだけでなく、子どもの脳の発達に長期的な良い影響を与えます。
自己肯定感の形成メカニズム
子どもの行動の裏にある才能や資質を認める声かけは、「自分は価値ある存在だ」という自己肯定感を育みます。脳科学研究によれば、肯定的なフィードバックを受けた子どもの前頭前皮質(判断や意思決定を司る部位)は活性化し、健全に発達することが示されています。
特にパパからの「認められている」という感覚は、子どもの脳内でオキシトシン(信頼や絆のホルモン)の分泌を促進し、安心感と自己肯定感を高めます。
レジリエンス(困難に立ち向かう力)の育成
「失敗してもいい」「挑戦することが大事」というメッセージを含む声かけは、子どものレジリエンスを育てます。ストレスや逆境に対処する能力を形成する脳の神経回路は、特に4〜12歳の間に発達するといわれています。
この時期にパパから適切な声かけを受けた子どもは、困難な状況でも「やればできる」「解決策はある」という思考回路が自然と働くようになります。
挑戦する姿勢と失敗からの学びを促す効果
子どもの「困った行動」を単に抑制するのではなく、その裏にある前向きな側面を認め、より適切な方向に導く声かけは、子どもの「成長マインドセット」を育てます。
スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエック博士の研究によれば、「頭がいいね」という結果を褒める声かけよりも、「よく頑張ったね」という過程を認める声かけの方が、子どもの挑戦意欲と粘り強さを育てるといいます。パパからのこうした声かけは、子どもの脳に「挑戦することで成長できる」という回路を形成します。
将来の成功につながる非認知能力の発達
「困った行動」の裏にある資質を認め、それを適切に導く声かけは、子どもの「非認知能力」(感情コントロール、忍耐力、協調性など)の発達を促します。これらの能力は、学業成績よりも将来の社会的成功により強く関連することが、複数の長期研究で示されています。
父親からの適切な声かけは、特に「感情調整」と「目標達成に向けた粘り強さ」という非認知能力の発達に強い影響を与えることがわかっています。
親子の信頼関係構築における声かけの役割
「あなたの行動は問題だけど、あなた自身は素晴らしい」というメッセージを一貫して伝える声かけは、深い親子の信頼関係を築きます。この信頼関係は、思春期や青年期の困難な時期にも揺るがない絆となります。
特にパパとの安定した関係は、子どもの対人関係能力の発達に重要な影響を与え、将来の健全な人間関係の基盤となります。「困った行動」の瞬間こそ、この信頼関係を深める貴重な機会なのです。
【体験談】声かけで子どもが変わった3つのケース

実際に「声かけ」によって子どもの行動や特性が変化した事例をご紹介します。
【ケース1】「落ち着きのない子」から「好奇心旺盛なリーダー」へ
6歳の息子は、幼稚園で「落ち着きがない」と指摘されることが多く、集団行動が苦手でした。しかし、その行動の裏には「知りたい」「試したい」という強い好奇心があると気づいたパパは、声かけを変えてみました。
「なぜそれが気になるの?」「その方法で試してみたんだね、面白いね」と、好奇心を肯定する声かけを続けたところ、少しずつ変化が。自分の興味を言葉で表現できるようになり、幼稚園でも「探検隊長」として友達を率いるポジティブな役割を見出すようになりました。
成功のカギ: 「問題行動」ではなく「好奇心の表れ」と捉え直し、言葉で表現する方法を教えたこと。
【ケース2】「かんしゃく持ち」から「感受性豊かな共感力の高い子」へ
4歳の娘は感情の起伏が激しく、ささいなことで大泣きしたり怒ったりすることが多く、両親は対応に苦慮していました。しかし、「感情表現が豊か」という視点に立ってみると、娘は他の子の感情にも敏感に反応することに気づきました。
「そんなに悲しかったんだね」「その気持ち、すごくわかるよ」と感情を認める声かけを続けたところ、娘は少しずつ自分の感情を言葉で表現できるようになりました。さらに、友達が転んで泣いていると「大丈夫?痛かったね」と声をかけるなど、その感受性を他者への思いやりとして発揮するようになったのです。
成功のカギ: 感情表現を否定せず、その豊かな感受性を「強み」として認めたこと。感情を言語化する手助けをしたこと。
【ケース3】「こだわり強すぎる子」から「集中力のある専門家タイプ」へ
8歳の男の子は、特定のテーマ(鉄道)に異常なほどこだわり、それ以外のことには興味を示さないことが心配されていました。学校でも「融通が利かない」と指摘されることが多かったそうです。
しかし、そのこだわりを「専門性」「集中力」と捉え直したパパは、「鉄道のことをそんなに詳しく知っているなんてすごいね!」「その集中力は特別な才能だよ」と声をかけるようにしました。また、「鉄道の模型とプログラミングを組み合わせると動く模型ができるかも」など、興味の幅を少しずつ広げる提案も。
結果として、子どもは鉄道への興味を保ちながらも、プログラミングや科学、さらには鉄道の歴史など関連分野にも興味を広げていきました。集中力と探究心は彼の強みとなり、学習面でも力を発揮するようになったのです。
成功のカギ: こだわりを否定せず「専門性」として認め、それを基点に興味の幅を広げる手助けをしたこと。
これらのケースに共通するのは、「困った行動」の裏にある才能や資質を見抜き、それを認める声かけがなされたことです。子どもは自分の特性を「悪いこと」ではなく「特別な才能」として理解することで、それを適切に活かす方向へと成長していったのです。
まとめ:明日から実践できる3つのステップ

ここまで紹介してきた「子どもの困った行動を才能に変える声かけテクニック」を、明日から実践するためのステップをご紹介します。
ステップ1:子どもの「困った行動」を記録する
まずは、子どもの「困った」と感じる行動を1週間ほど記録してみましょう。
- どんな状況で起きるのか
- その時の子どもの表情や様子
- その行動の裏にある可能性のある才能や資質は何か
この「観察」のプロセスだけでも、子どもの行動への見方が変わってくるはずです。
ステップ2:声かけのレパートリーを準備する
本記事で紹介した年齢別フレーズから、自分の子どもに合いそうなものを5つほど選んでメモしておきましょう。実際の場面で咄嗟に思いつくのは難しいものです。事前に「使える言葉」を準備しておくと安心です。
スマホのメモ帳に書いておくのも良いでしょう。また、冷蔵庫や玄関など、よく目にする場所に貼っておくのも効果的です。
ステップ3:小さな成功体験を積み重ねる
完璧を目指す必要はありません。まずは1日1回でも良いので、「困った行動」に対して肯定的な声かけを実践してみましょう。そして、その結果を簡単にメモしておくと良いでしょう。
小さな変化も見逃さず、「あの声かけが効いたかも」という成功体験を積み重ねることで、自然と声かけのレパートリーが増えていきます。
パパの声かけ一つで、子どもの「困った行動」は「輝く才能」へと変わる可能性を秘めています。子育ての大変さは変わらないかもしれませんが、その見方を変えることで、親子共に成長できる貴重な機会となるでしょう。
皆さんの声かけによって、子どもたちがどう変わったか、ぜひコメント欄でシェアしてください。
また、具体的な困りごとや質問にも、できる限りお答えしていきます。